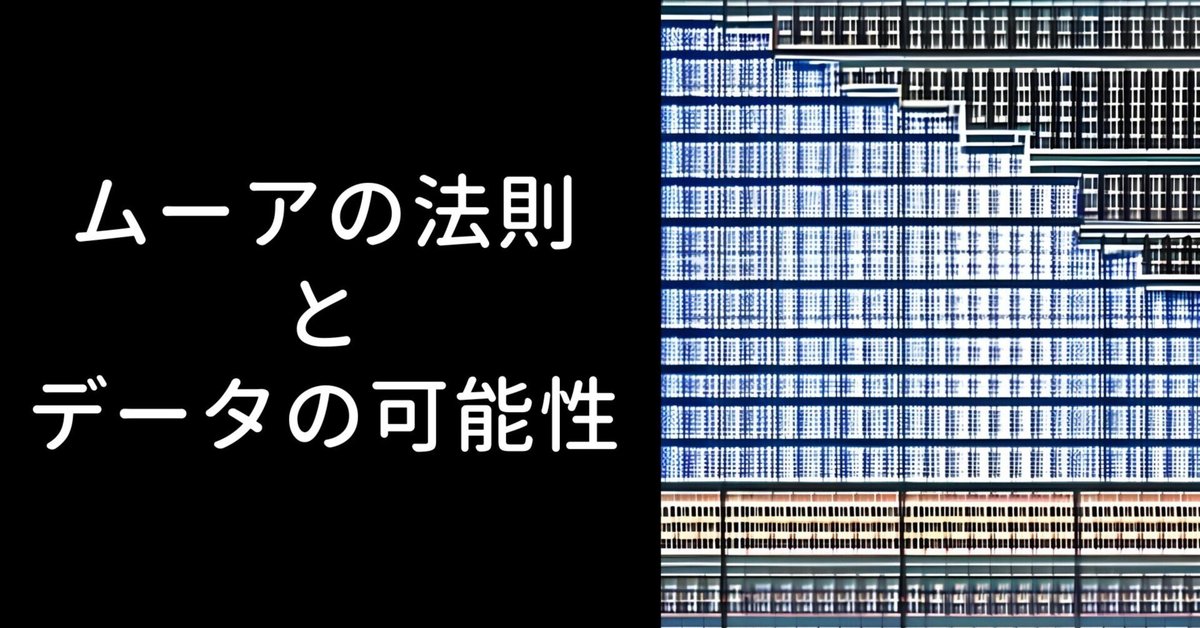
デジタルツインを超えて、「測る」の世界から「見える」の世界へ〜全量データは世界の解像度を上げる~
2023年3月、インテルの創業者の一人であるゴードン・ムーア氏がこの世を去りました。ムーア氏が1965年に提唱した半導体の集積率(面積あたりのトランジスタ数)が2年ごとに2倍になるという「ムーアの法則」は、コンピューターの処理能力を指数関数的に成長させました。それと共に、収集し、分析できるデータの量も指数関数的に増えています。
通信ネットワークやセンサー技術の進化により、さまざまな種類のデータがリアルタイムで取得できるようになりました。これらに加えて、行政が公開しているオープンデータ、企業が保有している生産情報、販売情報、顧客情報、取引情報などのさまざまなビジネスに関わる情報、インターネット上にあるSNSの情報などの情報を集めた「ビッグデータ」とそれを分析する技術は、AI、IoT、ロボティクスなど、これからの社会を支えるサービスの創出、働き方の変革、社会課題の解決などに資するテクノロジーの基盤であり、その重要性が増しています。
一方で、ビッグデータとよく似ているけれども少し違う概念として、「全量データ」という概念があります。全量データという切り口で技術の進化と情報量の関係をたどると、今まで見えなかったものが見える可能性を感じます。
目次
■現実世界を「測る」ことで構成されるデジタルツイン
■技術の進歩と共に情報量が増える全量データ
■世界の解像度を上げて、見えることを増やす
■知らなかった自分に気づき、より良い生き方を助けるサービスへ
■現実世界を「測る」ことで構成されるデジタルツイン
ビッグデータが、多様な種類のデータをさまざまなところから集めた大量のデータであるのに対し、全量データは、「ある特定の対象についての全てのデータ」です。例えば、Twitter社は全てのツイートのデータを「ツイートの全量データ」として販売しており、マーケティング企業がそれを分析して商売のネタにしています。
IoTや通信技術の進化により実用化が見えてきたのが、「フィジカルな世界を対象にした全量データ」です。対象には人、動物、機械などのオブジェクトそのものや、その動き、関係などさまざまなものが入ります。
IoTの活用例として挙げられる「デジタルツイン」は、全量データを使ってサイバー空間上にフィジカル空間のコピーを再現し、物理的なシミュレーションができる技術です。例えば工場の製造ラインのデジタルツインを作って動かすことで、ボトルネックを把握したり、機械の故障予測に活用し、現実の工場のラインの改良や機械の予防保守に役立てます。医療分野では、人体と手術で使うドリルなどの医療機器のデジタルツインを作って動かしてみることで、実際に掘削した脊髄の変形や神経の露出などをシミュレーションしている例があります。交通分野では、自動車や道路システムのデジタルツインを作って、都市計画への活用や日々の渋滞予測、事故発生時の最適な迂回ルートの探索などへの応用が研究されています。
フィジカルな世界を全量データに変換する時に考慮から抜けがちなのが、「何をデータ化して、何をデータ化しないのか」ということです。これは、データ化するために使える手段や技術に依存します。デジタルツインの場合、センサーで取得した値を全量データとして扱いますが、何をセンサーで測定し、何をモデルに取り込むのかは、人が決めます。言い換えると、デジタルツインの世界は、「これを測ることに意味がある」と人が判断した(かつ、技術的に測定可能な)項目で構成されており、それ以外の情報は欠けた世界です。
■技術の進歩と共に情報量が増える全量データ
一方で、何を測るかを人が決めず、その時使える手段を全て使って記録したデータを全量データとして扱うというアプローチもあります。この考え方では、記録に使う技術が変わると全量データに含まれる情報量も変わります。言葉だけではイメージしづらいので、例えば「会議という場」を、全量データに変換することを考えてみましょう。
録音技術が一般化する前は、(速記録の技術を持たない人にとっては)その場での発言を全て記録することは困難でした。聞き取った内容の要点が書かれた紙のメモがその会議の全量データでした。やがてカセットテープが普及すると、誰でも発言を音声でそのまま記録・再生できるようになり、全量データの情報量が増えました。さらにビデオカメラが普及すると、音声だけでなく映像も記録・再生できるようになり、言葉にならない手振り、表情、席順、その日の服装などの情報も、全量データに追加されました。記録技術の進化により、全量データの情報量が増えていったのです。
全量データをデジタル化することで、人ではなくコンピューターが全量データを扱えるようになりました。すると、音声認識技術や映像解析技術が全量データを読み取り、新たな情報を見出せるようになりました。例えばそれは、会議の参加者がその場で無意識に行っている「Aさんは怒っている」「Bさんは嘘をついている」といった推察を、感情認識AIが全量データから読み取るようなことです。人によっては見落とすこともある「間」や「息遣い」なども、トレーニングされたAIであれば漏れなく読み取ることができます。

■世界の解像度を上げて、見えることを増やす
全量データの記録技術と解析技術の発達により、今まで見えなかったことが誰にでも見えるようになります。それは世界を見る解像度を上げ、「見えること」を増やす技術だと言えるかもしれません。それにより、生活がもっと便利になったり、安全になったりする可能性があります。わかりやすいのが医療の例です。
医師にとっての患者の全量データは、その昔は問診と聴診の結果を医師が記入した紙のカルテでした。そこにレントゲン、内視鏡、CTスキャンなどの画像や映像情報が加わり、さまざまな角度から医師は患者を見て診断できるようになりました。今は、カルテの情報も画像情報も全てデジタル化されています。それらの全量データをAIが読み取って過去の症例などと照合し、考えられる診断の候補を医師に提示する、といったことが既に可能になっています。データを並べてみて比較し、場合によっては過去の症例や論文を検索する、といった作業を医師が行う必要がなくなり、その時間を患者との応対に充てることができます。
さらに、ウェアラブルデバイスによるバイタルデータの常時測定や、家庭で測定したデータも、リアルタイムで電子カルテシステムに送信し、全量データに統合することも可能になります。それをAIが分析して危険な兆候を検知し、医師にアラートを出せれば、診察に来ていない患者を診断して緊急搬送処置を手配することもできるようになるでしょう。今まで見えなかった「病院にいない時の患者」が見えるようになり、命を守れるようになるのです。
■知らなかった自分に気づき、より良い生き方を助けるサービスへ
これから重要になってくると思うのは、「人」そのものを表す全量データです。昔であれば日記をつける、ライフログを残すといった自分自身の行動により記録を残していましたが、今はその気になれば自分の行動記録をデジタルデータとして自動取得することが可能です。位置情報はGPSで、動作はモーションキャプチャや加速度センサーで常時測定可能です。誰と会い何を話したかはスマートフォンで簡単に記録できます。キャッシュレスで買い物すれば何をどこで買ったかの記録は全てデジタルデータとして残ります。ネット上の行動履歴はログで残ります。スマートウォッチで呼吸数、心拍数、血圧などのバイタルサインは常時記録できます。そのうち、セロトニンやオキシトシンなどの感情を司る化学物質の変化も測定できるようになるかもしれません。これらの全量データを把握しAIで分析することができれば、自分でも知らなかった自分に気づき、コントロールすることができるようになるはずです。
猫の例ですが、首輪につけたセンサーで食事、遊ぶ、寝るなどの行動を、トイレにつけたセンサーとカメラで排泄のタイミング、量、映像を記録し、AIで分析することで、猫の健康状態チェックや生活改善に役立てるサブスクサービスがヒットしています。人の全量データもAIで分析することで、例えばより健康になったり、ダイエットに成功したり、生活習慣を改善したり、お金の使い方を見直すといった、より良い生き方を手助けするサービスができるようになると思っています。
センサーや通信ネットワークの技術の進化、そして急速なAIの進歩により、全量データで見える世界の解像度はどんどん上がっています。見えなかったことが見え、それによって便利や安全や楽しさが増えることに、明るい期待を感じています。
参考:
デジタルツインとは?製造業や都市などでの活用事例8選(NECソリューションイノベーター)
https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sp/contents/column/20220701_digital-twin.htmlヘルスケアにおけるデジタルツインの活用とは?(Healthtech DB)
https://healthtech-db.com/articles/healthcare-digital-twin-technology
Catlog
https://rabo.cat/catlog/

